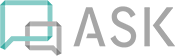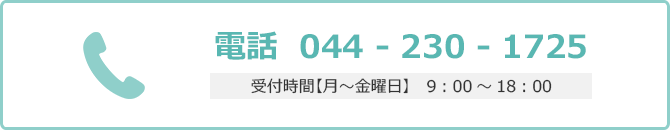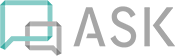被相続人は、遺言を残せば、遺産についていかようにも自分の財産を引き継がせることができます。
法定相続人でない人に、法定相続分と異なる財産を分け与えるのも自由です。
でも、本来の法定相続人にほとんど遺産の取り分がないことになると、相続人の生活が保障されなくなったり、少なくとも被相続人の財産が回ってくるはずだという期待にも反することになってしまいます。
そんなアンバランスを調整する制度が遺留分の制度です。
遺留分
遺贈や贈与がなされた場合でも、相続人には、最低限の法律で守られた権利があります。これを遺留分と言います。
遺留分減殺請求権(これまでの制度)
遺留分を実現するためには、遺留分権利者(遺留分を有する者)がその権利(遺留分減殺請求権)を行使する必要があります。行使しなければ、何にももらうことができずそのままです。
遺留分減殺請求権が行使されると、遺産である不動産や株式などが共有状態になります。
たとえば、遺産の中に不動産があり、遺贈を受けた者がその不動産に居住して、1人で生活を送っているような場合、遺留分権利者にとっては、その不動産が共有になったとしても、その不動産に居住できず、直ちに現金化することができるわけでもなく、共有になることのメリットがありません。
遺留分減殺請求権の行使があった場合でも、金銭を支払うことで和解することが多々ありました。
遺留分侵害額請求権(相続法改正による制度)
2019年7月1日に施行される改正民法では、この遺留分に関する規定が変わります。
「遺留分侵害額請求制度」となり、遺留分減殺請求権の行使による共有状態から生じる不都合を避けるために、侵害されている遺留分相当額の金銭の支払いを求めることができると規定されることになりました。
つまり、お金の支払いで解決しようというものです。
遺留分権利者およびその算定
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です(つまり、兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分はありません。)。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を算定するための財産の価額(「被相続人が相続開始時に有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「相続債務の全額」)に、次のそれぞれの割合および相続人自身の法定相続分を乗じたものが遺留分として有する額となります。
(1) 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
(2) 子や配偶者が相続人である場合など(1)以外の場合 2分の1
たとえば
・ 配偶者と子供2人が相続人の場合
遺留分の割合は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1に、法定相続分(配偶者:2分の1、子:4分の1ずつ)を乗じた割合になり、配偶者は4分の1、子はそれぞれ8分の1ずつが遺留分の割合となります。
・両親2人のみが相続人の場合
遺留分の割合は、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1に、法定相続分(それぞれ2分の1ずつ)を乗じた割合になり、両親は、それぞれ6分の1ずつが遺留分の割合となります。
生前になされた贈与
遺留分を算定するための財産の価額を計算する場合、「贈与した財産の価額」を加える必要がありますが、どのような贈与が加えられることになるのでしょうか。
・相続開始前の1年間になされた贈与は、無条件にその価額が参入されます。
・当事者双方(あげた方ともらった方双方)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与がなされた場合には、1年よりも前になされた贈与も参入されることになります。
・相続人が婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与(特別受益)の場合、
現在適用される民法では、期間の制限なく参入されていますが、
改正後は期間の制限が設けられ、相続開始前の10年間になされた贈与がその価額に算入されることになります。
受遺者または受贈者の負担額
受遺者(遺贈を受けた者)や受贈者(贈与を受けた者)が複数いる場合には、誰が遺留分侵害額を負担することになるのでしょうか。
・受遺者と受贈者がいる場合には、まずは受遺者が負担することになります。
・受遺者が複数いる場合または同時になされた贈与の受贈者が複数いる場合、その目的の価額の割合に応じて、案分して負担することになります。
・受贈者が複数いる場合、後になされた贈与の受贈者から順番に前の贈与の受贈者にさかのぼって負担することになります。
時効
遺留分減殺請求権には、時効があります。被相続人が死亡してから長期間経っても行使することができるわけではありません。
遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)は、被相続人が亡くなったことおよび減殺すべき(侵害する)贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があり、行使しないと、時効によって消滅してしまいます。
また、被相続人が亡くなった時から10年間経過したときも、同様に、権利が消滅することになります。