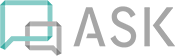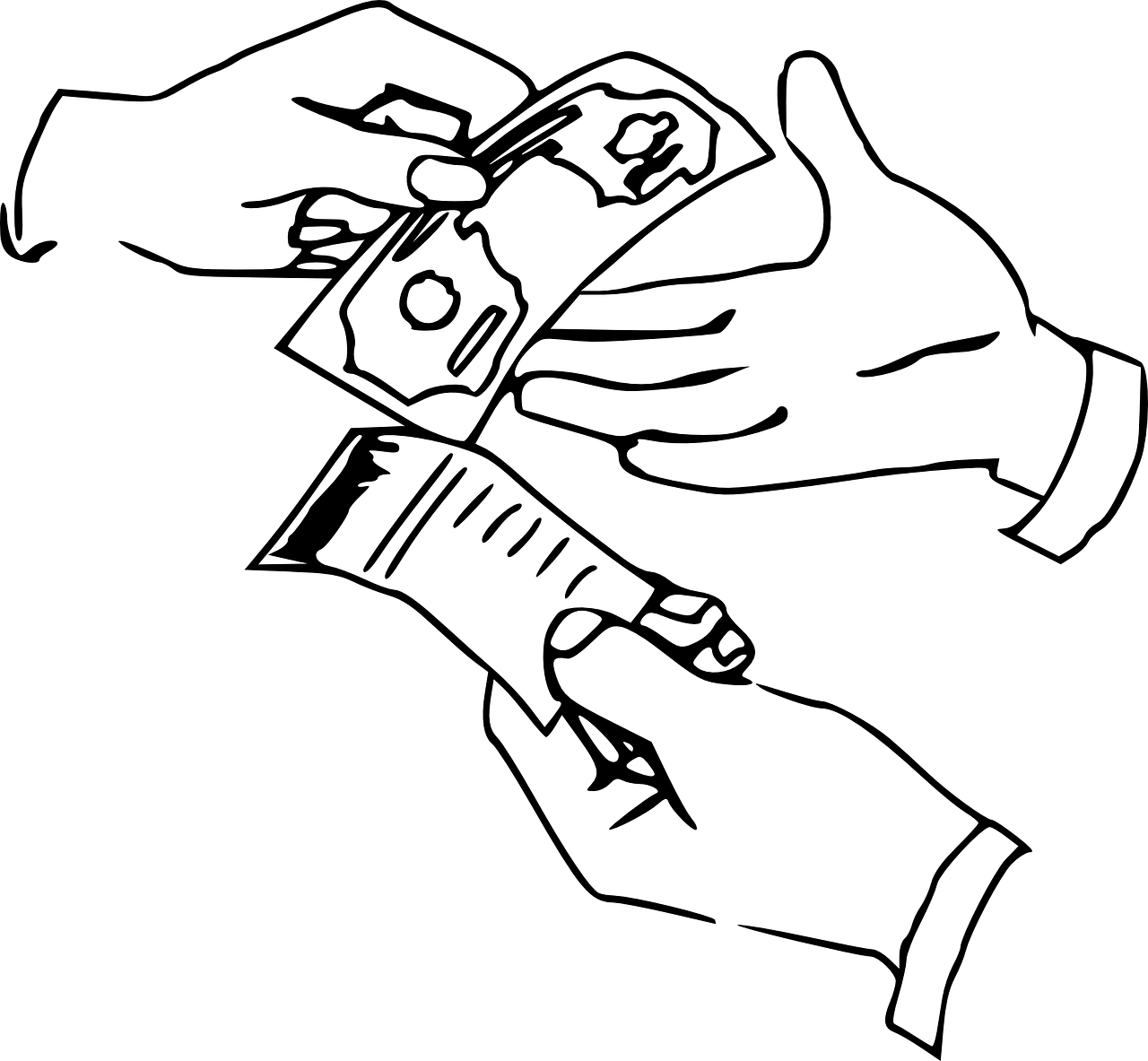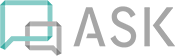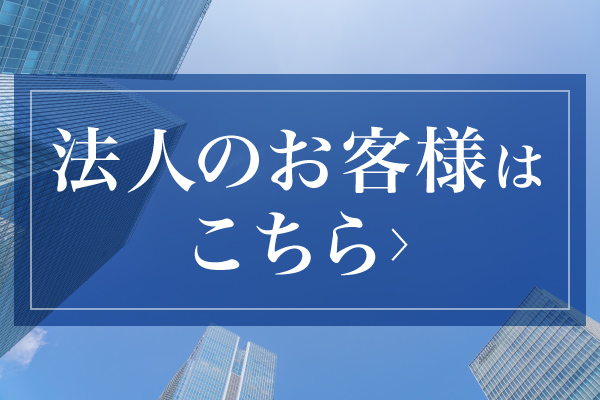個人であれば知人、友人との間で、法人であれば関係先との間で、都度お金を貸し借りする。ドラマなどでよく見るケースですが、そういうのってトラブルの元なのでは…???なんて思う方も多いのではないでしょうか。
しかも、それが何度も繰り返されて、過払金も発生していたら…
今回は、企業間で基本契約がないままに複数回の金銭授受が行われ、過払金が生じていたケースについて、それがお金の貸し借りの取引なのかどうか、貸し借りだとして過払金が出ていたらどう処理すべきかなどが問題となったケースを見ていきましょう。
事案の概要
- 本件の原告は、雑誌・書籍等の出版事業を営む株式会社であるX社です。
- 対して、被告は、不動産の調査業務等を業とするY1社とその代表者であるY2です(以下Y1及びY2をまとめて「Yら」といいます。)。
- XとYらとの間で、複数回にわたり金銭の授受が行われました。詳細は次のとおりです。
第1事件(X→Yら)
- Yらとの間で行った金銭の授受がいずれも継続的な金銭消費貸借取引であって、これに係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率により計算した金額を超えて支払った部分を元本に充当すると過払金が発生したとして、Y1に対して、不当利得に基づき、各取引に係る過払金の返還を求めた。
- Y2に対しては、不当利得に基づきY2との各取引に係る過払金の返還と会社法429条1項によるY1との取引に係る過払金元金相当額の支払いを求めた。
第2事件(Y1→X)
- Y1が、Xとの間で行った上記金銭の授受は、金銭消費貸借取引ではなく、Xが発行する書籍の売買契約を含むファンド契約であると主張して、Xに対して、売買契約に基づいて売買代金の支払等を求めた。
前提となる事実関係
XとYらとの間の取引関係
「取引行為1」:Xは、Y1との間で平成21年12月25日から平成29年2月6日までの間行われた金銭の授受
「取引行為2」:Y2との間で、平成17年9月7日から平成24年8月27日までの間行われた金銭の授受
※取引行為1と取引行為2を併せて「本件各取引」といいます。
売買契約とされる契約関係
XとYらは、平成21年12月25日から複数回にわたって、「『B2』第5版の翻訳出版に関して出版協力ファンドの契約書」と題する契約書を作成しました。
この契約の内容は、以下のようなものです。
◆Yらが出版協力ファンド先買権として、Xの出版発行する「B2」第5版の日本語翻訳版を予約で複数部買い取って、その後、XがY1に売却したこの書籍を買い戻す。
◆Yらによる本件書籍の買取価格の総額は、本件各取引のうち、平成21年12月25日のYらのXに対する入金額と同額で定められていた。
◆XとYらは、その後も、XがYらから金銭の入金を受けるに当たり、その大半について、本件各取引におけるXのYらに対する入金額に対応して本件契約書で定める買取価格を変更する等した契約書を作成した。
争点
本件各取引が、利息制限法1条の定める「金銭を目的とする消費貸借」に当たるか
本件各取引での過払金にかかる充当合意の有無
Yらの悪意の受益者該当性
Y2の本件取引1に係る法的責任の有無
裁判所の判断
本件各取引が、利息制限法1条の定める「金銭を目的とする消費貸借」に当たるかについて
「当たる」と判断しました。
理由
- ①まず、XがYらから金銭の入金を受けるに当たり、その大半について、本件各取引におけるXのYらに対する入金額に対応して本件契約書で定める買取価格を変更する等した契約があったが、これに基づいて書籍の引渡しがなされた事実はなく、Yらにおいてこの書籍を転売等する予定があったことも窺われないから、売買の予約や再売買は実態を伴うものではないと判断し、
- ②本件書籍の売上実績にかかわらず、XがYらの買い受けた書籍を全て買い戻すこととなっていて、しかも、買戻価格がいずれもYらによる買受価格を上回っていたことから、
- ③実質的には、Yらが書籍の買受金として支払った金員につき、その元本の返還を保証するとともに、その使用の対価を支払うことを合意したものだと評価できる、
と判断しました。
- ④さらに、書籍の買戻価格が確定金額であること、上記契約の時点で支払時期も定められていたこと、買戻に係る支払方法が約束手形によるものであったこと
から、利息付消費貸借契約と異なるものではないと判断し、「金銭を目的とする消費貸借(利息制限法1条)」に当たるとしました。
(参考)利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
本件各取引での過払金にかかる充当合意の有無
充当の合意が“ある”と判断しました。
理由
- ①貸主と借主との貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において、第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後、同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したときには、その貸主と借主との間で、基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、第1貸付け過払金は、第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず、第2の貸付けに係る債務には充当されないと解するのが相当であると判示した上で、(規範)
- ②本件取引1については、多数回にわたる貸付けと返済が繰り返されていること、Y2が本件取引1の当初に定期的な出資の依頼があることを認識していたことを認定しつつ、本件取引1は繰り返し同様の貸付けがなされることが想定されており、事実上1個の連続した取引であると判断し、本件取引1に基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払金が発生した場合には、前記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとしました(当てはめ)。
- ③一方で、本件取引2については、貸付けの回数が少なく、取引の間隔も大きいことを理由に1個の連続した貸付取引であるとはいえないと判断しています(当てはめ)。
Yらの悪意の受益者該当性
悪意の受益者該当性を“否定”しました。
理由
- ①本件各契約書の表題・形式から、直ちに、本件各契約を金銭消費貸借であるものと認識することはできず、Y2においても、本件各取引が金銭消費貸借取引であり、これに利息制限法が適用され、Yらが同法所定の制限利息を超過する利息を法律上の原因なく利得していることを認識していたということはできないとし、Yらが悪意の受益者に当たらない、としたのです。
- ②そして、Y1に係る残債務額を1億3330万8900円、Y2に係る残債務額を345万8048円と認定しました。
Y2の本件取引1に係る法的責任の有無
Y2の責任を“否定”しました。
理由
- ①上記と同様の理由から、結局のところ、Y2が、本件取引lが利息制限法1条3号に反することについて悪意又は重過失があったことということはできず、また、Y2がY1の法人格を濫用したことを裏付ける的確な証拠はないとして、いずれもこれを否定しました。
解説
これまでの最高裁による判断の蓄積
充当に関する指定の存在を推認する方向での判断の存在
貸主と借主との間で継続的に金銭消費貸借取引が繰り返されている場合に、1つの借入金債務に対する弁済から生じた過払金を他の借入金債務に充当することができるかにつき、貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的な金銭消費貸借取引がなされている場合については、借主は借入れの減少を望み、複数の権利関係が発生することを望まないことが通常であるとして、当事者間に充当に関する特約が存在するなどの特段の事情がない限り、借主が1つの借入金債務に対する弁済との関係で生じた過払金について、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したと推認されると解されています(最二小判平15・7・18)。
金銭消費貸借取引当事者間に基本契約がない場合においては特段の事情がない限り、充当はされないとする判断の存在
貸主と借主との間に基本契約が締結されていない場合については、第1の貸付けに係る債務の弁済との関係で過払金が生じた後、第2の貸付けに係る債務が発生したときには、その貸主と借主との間で、基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主との間に第1の貸付に対する弁済との関係で生じた過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、第1の貸付けに対する弁済との関係で生じた過払金は、第1の貸付けに係る債務の弁済が第2の貸付けの前にされたものであるかにかかわらず、第2の貸付けに係る債務に充当されないと解されており、本判決でも言及があったものです(最三小判平19・2・13)。
本事案での特殊性を踏まえた、「特段の事情」の肯定
以上のような判断はあるものの、本件では、上記平成19年の最高裁判断が言う「特段の事情」に当たる事実があったものと判断し、充当の合意の存在を認めたものです。
さいごに
今回取り上げた事例は、なかなかお目にかかることのない特殊な事案ともいえるかもしれません。
とはいえ、お金の貸し借りに関する困りごとは身近に生じやすいトラブルのひとつともいえます。
弁護士法人ASKでは、金銭トラブルに関するご相談も受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ!