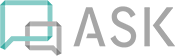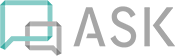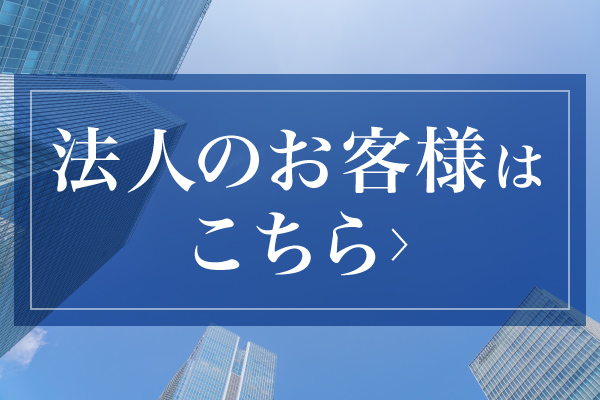我々の業務において「民法」に触れない日はないと言っても過言ではありません。
その民法も、近時は重要な改正が続いています。
今回ご紹介する事案は、正に平成30年改正で創設された配偶者居住権に関する判断(審判)がなされた福岡家裁令和5年6月14日です。
亡くなった配偶者が所有する不動産に、そのまま住み続けたい他方配偶者には、どのような権利が認められ、遺産分割にはどう対応すればよいのでしょうか。今回のケースはそんな問いにひとつのヒントを与えてくれるかもしれません。
事案の概要
前提となる事実
被相続人Zが死亡し、相続が開始しました。
Zの相続人は、妻B(本件遺産分割調停の相手方、80代)、ZとBとの間の子C(同じく相手方)、Bの子でZの養女、養子であるA(申立人)とPです。
当事者の範囲
Pは、遺産分割調停の申立前に、自身の相続分をAに譲渡したため、本件遺産分割ないしは同調停の当事者は、A(相続分は6分の2)、B(2分の1)及びC(6分の1)の3名となります。
遺産の範囲と当事者の意向
Zの遺産として、土地及び建物がありました。
Bは、本件建物につき、B自身が亡くなるまで配偶者居住権を取得し、今後も本件不動産に住み続けたいとの意向でした。なお、Bは、Zの生前、本件不動産にZと一緒に住んでいました。現在は、本件不動産にひとりで暮らしています。
Aは本件不動産の取得希望はなく、相続分を金銭で取得することを望んでいます。
Cは、配偶者居住権が設定された本件建物を取得することを了承しています。
裁判所の判断
結論
Bに本件建物につき、Bの終身の間配偶者居住権を取得させ、Bに本件建物の所有権を取得させるのが相当であるとしました。
※なお、Aは、Bが配偶者居住権を取得するなどしたことから、その評価を前提としA自身の相続分に応じた金銭を受け取ることができます(代償分割)。
理由
Bが配偶者居住権の設定を希望していること、Cがその設定された建物の取得を了承していること、それによるCの不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があることなどが理由となっています。
配偶者居住権の評価
相続においては、遺産等の金銭的評価が欠かせません。そこで、裁判所は、Bに取得を認めた配偶者居住権について、以下のような評価としました。
①本件土地及び建物の合計現在価額=356万4660円
②負担付建物所有権の価額=0円(法定耐用年数超過のため)
③負担付土地所有権の価額
=225万5940円(①の土地分)×0.744(83歳女性の平均余命10年を存続期間とするライプニッツ係数)
≒167万8419円
④配偶者居住権の価額
=①−(②+③)=188万6241円
配偶者居住権について
配偶者居住権は長期と短期の2種類
配偶者居住権は、以下に見るとおり、長期の配偶者居住権と短期の配偶者居住権とに分類できます。
(配偶者居住権)
第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(略)
(配偶者短期居住権)
第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
今回は、長期の配偶者居住権の事案であり、また、1029条2号の「配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。」が問題となった事案です。
本件のBは、高齢であり、長年その建物に居住し、今後もそこでの居住を希望していること(裏を返せば、これからの転居は負担が大きいこと)のほか、Cがそれを了承していることなどが比較衡量されたものといえ、妥当な結論といえそうです。
また、遺された配偶者は、遺産分割協議中、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合であれば、1037条の定めに従って一定期間は遺産の不動産に無償で住み続けることができるケースがあります。
さいごに
配偶者居住権は、生活の本拠を確保するために重要な権利といえます。そして、それは今回のようにして設定される場合だけでなく、遺贈の目的として設定することもできます。つまり、遺産分割で争いが生じて配偶者居住権の問題が出てきた場合はもちろん、遺された配偶者の生活の本拠を確保するため遺言作成段階で手当てを考えておくことも可能です。
生活の本拠をどうするかはとても重要な問題です。配偶者居住権はそれにひとつの指針を示す大きな改正であり、今回ご紹介した事案は、その成立や評価方法などについて判断した有用な実例といえそうです。
配偶者居住権をはじめ、相続についてお困りごとがあれば、是非弁護士法人ASKにお問い合わせください。
問い合わせは、こちらから!