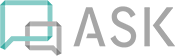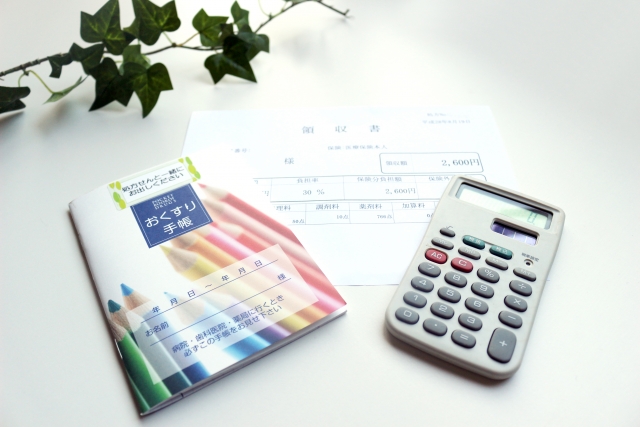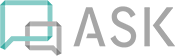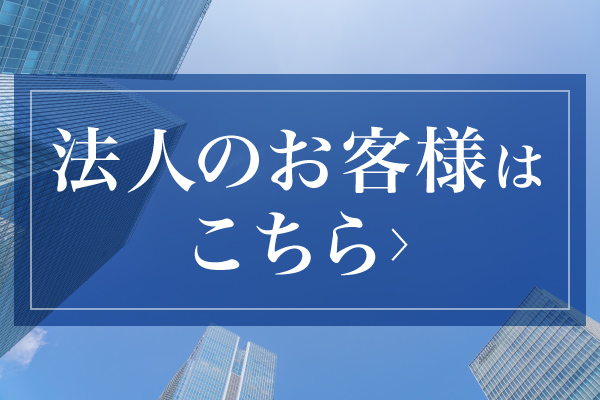事故などによって不幸にも人命が失われた場合、その損害賠償を求めるに当たっては、「逸失利益」として、本来であれば得られたであろう利益が失われたとしてその分の請求をすることがあります。
今回ご紹介する事案は、その「逸失利益」に、国民年金法30条の4第1項に定められた無拠出制の障害基礎年金が含まれるかどうかが争点となったケースです(大分地裁令和6年3月1日判決)。
事案の概要
Z(当時17歳):知的及び身体的障害を有し、大分県(Y)が設置する特別支援学校高等部に通学していた高校生です。給食時間中に倒れ、後に死亡しました。
Xら:Zの親族
Y:学校設置者たる大分県
➡Xらが、Yを相手取り、まずは民法715条に基づく、それが認められなかった場合には国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求等を求めた事案です。
争点
本事案で争点とされたのは次のポイントです。
①Yが民法715条に基づく使用者責任を追うか
②支援学校職員の注意義務違反の有無
③注意義務違反と死亡との因果関係
④Xらの損害
➡このうち、①〜③は肯定されました(詳細は本稿では省略)。
④詳説
上記ポイント④はどう判断されたか。
国民年金法30条1項所定の障害基礎年金(拠出制の障害基礎年金)は、傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、国民年金の被保険者であることが受給要件の1つとなっています。
➡具体的には、被保険者は、
❶国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者…
❷厚生年金の被保険者…
❸第2号被保険者の配偶者
とされています(同法7条1項)。
➡そうすると、既に障害を有していたZは、本件事故当時17歳であって拠出制の障害基礎年金を受給する可能性は高くないといえます。
では、本件Zのような、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したとき以降に受給し得る無拠出制の障害年金(同法30条の4第1項)が逸失利益として認められるか。
判決の結論
逸失利益性を否定しました。
理由
裁判所は、次のように述べています。
「同法30条1項に基づく障害基礎年金は、原則として、保険料を納付している被保険者が所定の障害等級に該当する障害の状態になったときに支給されるものであり、保険料が拠出されたことに基づく給付としての性格を有している。
一方、同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金は、被保険者資格を取得する20歳に達する前に疾病にかかり、又は負傷し、これによって重い障害の状態にあることとなった者に対し、一定の範囲で国民年金制度の保障する利益を享受させるべく、同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨で設けられた無拠出制の年金給付であるとされる(最高裁平成17年(行ツ)第246号同19年9月28日第二小法廷判決・民集61巻6号2345頁参照)。
そして、同法は、同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金について、刑事施設等に拘禁されている場合の支給停止(同法36条の2第1項)や所得制限による支給停止(同法36条の3第1項)等の支給停止事由を定めているところ、これらの支給停止事由は、同法30条1項に基づく障害基礎年金については定められていない。
そうすると、同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金は、拠出した保険料とのけん連関係があるものとはいえず、社会保障的性格が強いものであるというべきであり、同法30条1項に基づく障害基礎年金とは直ちには同列には解し難い。
したがって、Zが同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金を受給していた蓋然性があったと認められたとしても、同年金がZの逸失利益であると認めるのは困難であるというほかないから、原告の前記主張は採用し難いものといわざるを得ない。」
以上の理由で、無拠出制の障害基礎年金の逸失利益該当性を否定しました。
まとめ
これまで、拠出制の障害基礎年金は、その逸失利益該当性が認められていましたが、反対に、無拠出制の障害基礎年金については判断が分かれていました。下級審裁判例でもあり、影響の及ぶ範囲は限定的と思われますが、参考に値する判断といえるでしょう。
このように損害論は、理論上も難しい論点を含んでおり、専門的知識が欠かせません。
事故などでお困りの際には、弁護士法人ASKまでお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら➡https://www.s-dori-law.com/contact