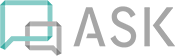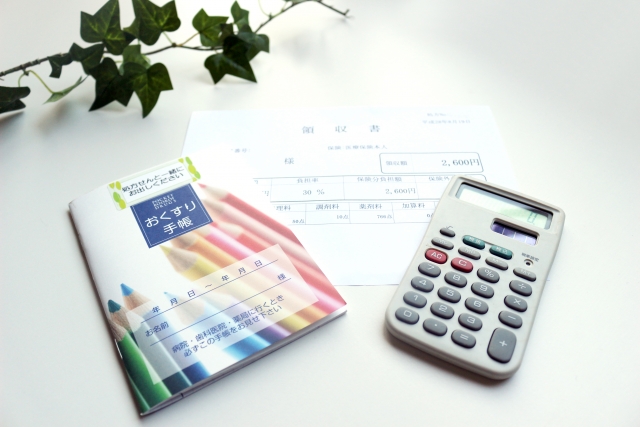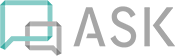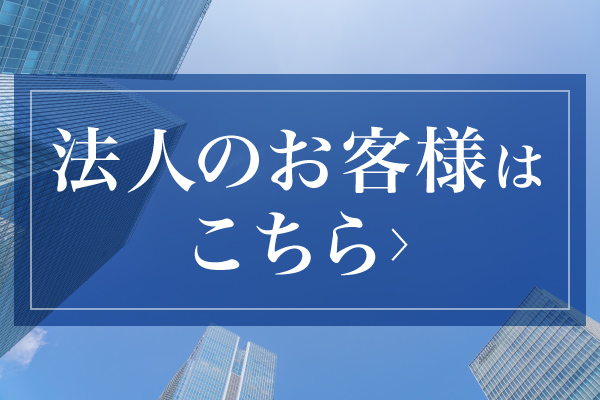事故により人が亡くなってしまったり、後遺障害が残ってしまったりしたような場合には、逸失利益といって、本来であれば得られたであろう将来の収入が死亡や後遺障害があることによって得られなくなってしまったことを理由に、その賠償を求めることができます。
今回は、その逸失利益について、事故により死亡した児童が重度知的障害を有していた場合に、逸失利益を算定するに当たって基礎とすべき基礎収入について、賃金センサスの全労働者平均賃金の5割相当額を算定ベースとした事案である山口地裁令和5年12月20日判決をご紹介します。
逸失利益とは
逸失利益の意義
そもそも逸失利益とはなんでしょうか。
逸失利益とは、事故によって死亡に至ってしまったり後遺障害が生じてしまったりしたとき、それによって、本来であれば得られたであろう将来の収入が減ったものとして、その減少した分を損害と観念するものです。つまり、死亡や後遺障害があることによる将来の収入の減少分を損害として請求するものです。
算定方法
逸失利益とは上記のような損害です。そうすると、将来という現時点では確知し得ない要素を含むものですから、一種のフィクションともいえます。この一種のフィクションをどう算定するかが問題になります。
この点について、実務上の取扱いとしては、働いて収入を得ている人であれば、事故前の年収は分かりますのでそれを基に算定します。
では、本件のようにまだ学齢期にあるような方や主婦(主夫)などが被害者となったりした場合はどうするか。
その場合、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果を利用して、年収を措定した上で算定することとなります。この「賃金構造基本統計調査」を一般に賃金センサスと呼称しています。
(※賃金構造基本統計調査は、 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.ht から閲覧可能です。)
この前提知識を踏まえ、本事案を見ていきましょう。
事案の概要
被告が運営する施設を利用中の原告らの子であるAが、同施設を出て外のため池で溺死する事故(以下「本件事故」という。)が発生しました。本件は、原告らが、被告に対し、本件事故は、被告の安全配慮義務違反並びに被告職員ら及び被告法人の過失によるものであると主張して、債務不履行及び不法行為(使用者責任及び法人の不法行為)に基づき、相続分に応じ、それぞれ慰謝料等3528万9346円及びこれに対する本件事故日である令和3年8月19日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案です。
ところで、本件事故で亡くなったAは、平成31年1月22日、H1病院において、自閉症スペクトラム障害(以下「ASD」という。)の診断を受け、その後、S5児童相談所において1種知的障害者の判定を受け、令和2年12月28日、療育手帳の交付を受けています。そして、Aは、令和3年4月、山口県立S2支援学校(以下「支援学校」という。)に入学し、同月以降、毎週木曜日、支援学校に通学した後、本件サービスを利用し、支援学校の夏休みが開始した同年7月21日以降は、毎週木曜日、午前中から本件サービスを利用するようになりました。
被告は、本件事故日である令和3年8月19日当時、有限会社S3から建物内の一部を賃借して、放課後等デイサービス事業を行っていました。他方、賃借部分以外では改装工事が行われていました。
事故時の状況としては、Aが、本件事故当日、被告の専有部分から、そうではない部分の部屋を通過して、本件建物外へ出て、建物から約700m離れたため池まで移動し、そのため池で溺死しました。
争点
本件では、争点がいくつかあり、その中でも主に①被告の債務不履行又は不法行為責任の有無、②Aの逸失利益額が論点となりました。結果的に、①は肯定され、被告である施設側の責任が認められることとなりましたので、以下では②を中心に説明をしていきます。
本件において、②は、次のように問題となりました。
すなわち、Aが重度知的障害のある7歳の児童であったため、逸失利益の算定に当たって計算の基礎となる基礎収入につき、原告ら(Aの親)は、Aには一般就労を前提とする平均賃金額を得られる蓋然性があったとして、令和元年度の全労働者の平均賃金(500万6900円)の8割が相当であると主張しました。
他方、被告は、Aが雇用契約に基づく就労が可能となる程度の稼働能力を身につける蓋然性があったとはいえない等主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、具体的事実を認定した上で、「Aが障害のない児童と比べて相当に後れを取っており、将来においてもその差の解消が困難であることを否定することはできないものの、Aが将来の社会における職場環境の整備等と相まって、社会生活上の障害に折合いをつけ、得意な分野における能力を伸ばしていく可能性は十分にあるから、将来、障害者雇用が促進され、多様な働き方が認められた社会において、長年にわたるその就労可能期間のいずれかの時点では自身の長所を活かした稼働能力を発揮する蓋然性が認められる」とし、障害者雇用者の平均賃金額を逸失利益算定の参考にするのは相当でなく、「基本的には、上記のような障害を有していたとして年少者であるAの逸失利益を算定するには、全労働者の平均賃金を参考にすべきであると解するのが相当である」としつつも、一方で、「Aの潜在的な稼働能力がいつどのような形で顕在化するかは不明と言わざるを得ず、法制定以降、障害者雇用の状況は改善されているものの、現時点においても、障害のある労働者とそうでない者との差が十分に埋められているわけではなく」、「知的障害については、身体的機能及び精神的機能の全てを司る脳に障害があり、発達障害も個々によって状態は様々であることから、周囲の支援等を含む総合的かつ個別具体的な支援が必要であって、潜在的な稼働能力が顕在化しても、直ちにその能力を最大限活用することが可能とも言い難い場合がある」から、「Aの基礎収入額については、就労可能期間の全体を通じて、全労働者の平均賃金の5割に相当する年収(244万6550円)とするのが相当である。」と判断しました。
解説
過去の判例(最高裁昭和39年6月24日判決)を踏まえると、不法行為により死亡した年少者が生前就労していなかった場合、逸失利益の算定における基礎収入の額は、その年少者が将来どの程度の収入を得られるかを予測して認定する必要があり、そのためには、あらゆる証拠資料に基づき、経験則とその良識を十分に活用して、できる限り客観性のある額を算出するように努めるべきであるとされています。
本件では、Aの生前の様子について具体的に認定した上で結論を導いており、逸失利益という将来予測を含む難しい点について、上記過去の判例が示した方向性に基づいて精緻に結論を導いているものといえるでしょう。
本論点が争われた類似事案は多くあり、最近では、大阪高裁で感音性難聴を有する11歳の聴覚支援学校に在籍していた女子児童が交通事故により死亡したしたケースの基礎収入額につき、全労働者平均賃金と同等の額とした判決が出されたことが広く報道されました(大阪高裁令和7年1月20日)。
なお、この事案の地裁判決(大阪地裁令和5年2月27日)では基礎収入につき、全労働者平均賃金の85%相当額と判断していました。
冒頭にも述べたとおり、逸失利益は、将来の事情を含む判断になるため、仮定的要素を多分に含むもので、その判断には難しさが伴います。
社会全体としてノーマライゼーションを推進していくことは是とすべき考え方であり、実際、社会的にそれを志向しているのが現代社会ともいえます。
一方で、損害賠償という制度は、金銭賠償によって損害の填補を行い、被害救済を目的とするものです。そのため、どうしても実績としての過去の統計等を利用することは避けられません。
障害がある場合の逸失利益の算定に当たり基礎収入をどう捉えるべきかは、このような点の相克が問題となる局面ともいえるのかもしれません。
最後に
損害賠償は、事故等の原因はもちろん、生じた損害についても高度な法的判断が求められます。賠償にまつわる問題が生じた場合には、是非弁護士法人ASKへご相談ください。お問合せはこちら